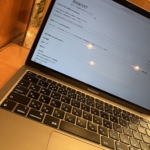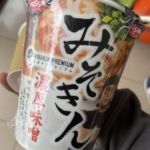昨日一昨日と仕事があって今日は休み、明日も仕事がある。
年末は紅白歌合戦を側見して、なごり雪を歌うイルカが昔よりだいぶ老け込んでいて、時の流れを感じた。ということは僕自身も、それなりに老け込んでいるということなんだろう。でも曲自体は変わることなく青春時代のノスタルジーを思い出させてくれる良い歌だった。僕の青春時代を思い浮かべる、といってもそんなたいそうな言葉で表現できるようなものでもない。
汽車を待つ君の横で僕は
時計を気にしてる
季節外れの雪が降ってる
東京で見る雪はこれで最後ねと
寂しそうに君が呟く
なごり雪も降る時を知り
ふざけ過ぎた季節の後で・・・

東京に上京していく地方都市を描いているのに、どうしてこうも胸を打つのだろうね。僕は上京する時の感傷に浸ったことはないし、電車と隔てた恋人との別れも特にあるわけじゃなかった。僕の青春時代を思い返してみるに、「儚い男女の別れ」というよりも、「告白しきれない自分自身の不甲斐なさ」が際立って思い出される。
ある女性とデートに行ってその三回目のデートの帰り際、僕は気恥ずかしさから告白をしきれずに、家に帰って冷静な気持ちの中でラインを送って告白した。もちろん上手くいかなかった。デート中その子は
「私、普通の人が好きなの、出過ぎたり尖り過ぎたりするわけでもなく、引っ込み思案でシャイすぎる人でもなく、普通の男の人なら何でもいいの」
僕はその言葉が僕への、遠回しの告白の言葉だと思った。僕は周りの人と変わらず出過ぎた真似はしないし、かといって女々しすぎるわけでもない、この子のタイプにぴったりな人なんだと。でも良く考えればそれが拒絶を意味する言葉だっていうのはその後になって分かったのだった。
他にもたくさんある。
気になる女性とラインを続けて何度かデートを重ねる。多分2、3回は行ったと思う。どこに行ったっけ、池袋のなんとかサンシャインの水族館だったような。ペンギンを二人で見て、クラゲの美しさに見惚れて、チンアナゴの不思議なシルエットに目が止まった。
「ほら、これチンアナゴだよ、こうき、知ってる?」
僕はチンアナゴの「チン」という発音がどうしてもいやらしく感じて(今思うととんでもない勘違いだと思う)、その単語を発することが男性としての卑しい下心を赤裸々に表してしまうのではないかと恐れて、
「知らないなぁ、変な、歪な形だね、初めて見たよ」
と相槌を打った。一度も「チンアナゴ」という固有名詞を使わずに何とか会話した。相手は何も気にしていなさそうな気配だったけど、僕は自分の下心が丸見えになってしまうのではないかとずっと背筋がゾクゾクしていた。

そのデート中には手を繋ぐことはなかったし、相手への想いを婉曲的にでさえ伝えることはできなかった。プラネタリウムで真っ暗の空間のまま席に横になって、光で照らされた美しい星々の煌めきを見つめた。その間中、手を繋ぐ絶好のチャンスとの想いが頭を掠めながらも僕は何もしなかった。それでも隣に横になっている美しい女性がいると思うといてもたってもいられず、定期的に唾をぐっと飲み込むのだった。多分あの唾をぐっと飲み込む音は、彼女にも聞こえていたと思う。どう思ったんだろう。情けないな。
あとになって諸々理由をつけて「この子のことを本当に好きではなかったから告白しなかったんだ、僕の告白できなかった消極さのその奥底に僕自身の答えがあるのではないか」って自分自分の不甲斐なさを正当化することもあったけど、結局のところその時気になった子への気持ちを直接に伝えることができなかっただけだった。それは相手へ思いを伝えることの気恥ずかしさからなのか何なのか。
今思い返してみると、それは自分の想いを一人の女性へ絶対化することを恐れていたのではないかと思う。自分の気持ちすべてをその一人の女性に預けるということがなぜだか心もとなかった、自分が自分でなくなるような気がした。自分の心の奥底に眠るありとあらゆる感情を相手に見透かされることの恐れというのか、どうしても他人と距離をとって壁を作らざるを得なかった。すべてを投げ出す、曝け出すことが怖くてたまらなかった、そのように今だと思う。
なんとまぁ情けない人生なんだろう、このようなエピソードがまだまだ五万とある気がする。そんな不甲斐なさと向き合うくらいなら誰とも付き合わない方がマシだと開き直ることさえ、できないでいる。

































のように、眼前に滞る無機質な時の流れが、ねずみ色の世界を形作る-150x150.jpg)