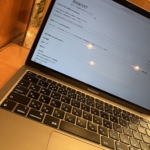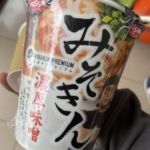家路へ向かう駅のホームにて、ふいに金木犀の香りがした。もうそんな季節なのか、いやいやそんな季節にはまだまだ早過ぎはしないだろうか、もしかしたらすれ違う誰かの香水か何かの間違いじゃなかろうか。
袖を捲って(そういえば長袖のシャツ着ていた)身につけているApple Watchから今日の日付を確認した。あぁもう10月だった。だとしたら金木犀が香ってきたとしても不思議はないだろう。見渡す限りにおいてはオレンジの身をつけた金木犀は見当たらないけれど、どこかしこに隠れて僕を誘惑しているの実があるのだろう、とそう思った。
金木犀の香りはいくつかの記憶を数珠つなぎに連想させる。それは僕にとっては母親の誕生日とイコールになる。母親は10月上旬の生まれでいつも自然の香りがその日の近いことを教えてくれる。と同時に母親の誕生日がイコール僕自身の不甲斐なさへと自然と結びつけられる。親孝行のための何かしらプレゼントなりを拵えておくべきことも毎年わざとすっぽかしている確信犯的な親不孝の自分がすぐに頭をよぎる。親の喜ぶことをするのが親孝行だとしたら、一般的な親は息子娘からのささやかなプレゼントを想起するだろうけど、うちの場合はどうも僕の感覚からすると、僕自身が僕自身のために、僕が僕らしく、生きる喜びを精一杯享受することこそが、母親への、もちろんそれは父親へも、最も大きなプレゼントであり、最大の親孝行なのではないかとそう思えてしまう、というのは僕のただの逃げ口上なのだろうか。
それに合わせてきのこ帝国の楽曲「金木犀の夜」が思い浮かべられる。きのこ帝国は10年代を代表するロックバンド(個人的に)でありながら、その後芸術性を捨て去り愚かな大衆慰安バンドと化してしまった最も僕らが憎んでしかるべきアーティストである。彼らの芸術性が娯楽性への移り変わってしまう頃合いにちょうど僕らが大学生時代を送っていたことを考えると、僕らの軽薄な娯楽性というものが彼ら魂を売った退廃的アーティストの所産であることは疑いないということから言って、やはり忌むべきバントの一つとするべきだという思いに至る。
さらに記憶は飛んで、きのこ帝国が好きだと公言していた大学時代の女友達のことに連想ゲームは映っていく。彼女は僕のことが多分好きだったしいつも僕のことを遠巻きから気にしていた。僕の一挙手一投足をすべて目に焼き付けようとしていたし僕の遺伝子を搾り取ろうと目が座っていることさえあったように思われる。あぁあの子とどうして付き合わなかったのか、付き合えなかったのか付き合わなかったのか、顔は可愛くてスタイルも十分だったのではないだろうか、性格もなんてことはない癖のない子だったようなそうでもないような。今頃あの子は今どこで何をしているのか、あぁあの子はきのこ帝国の中でも3rdアルバムが好きと言っていたし「ラストデイ」というエモエモな曲が一番ということだったが僕もあのアルバムは悪くないと思っていた。その次の4thアルバムから明らかに魂が死んで芸術性が捨て去られた風が感じられるようになったけど、3rdまでは、ギリ3rdまではよかった。もちろん1stが一番良いということは言うに及ばないだろう。
「魂が死んだ!」
「ああ僕らの魂が死んだんだ!」
「2010年代に入るあたりから、僕らの魂が死んだんだ!」
「僕らはただの魂の抜け殻だ!生きてなんかいない!僕の魂はどこかに消えてなくなった!」
「残ったのは蝉の抜け殻みたいな、人間の抜け殻だった!」
「あぁどうでもいい!すべてがどうでもいい!ああでもないこうでもない、もう何にでもないんだ!」
「神は死んだって死んでなくたってどうだって良いけれど、魂は絶対に死なせてはならないんだから!」
魂が死ぬ前の最後の輝きというものが、(うーんそれは輝きというほどものでもないかもしれない、輝きというのはnumber girlみたいなxjapan,luna seaみたいな芸術的爆発を伴うもので)、最後の輝きという言葉には誤謬が含まれていた、正しくは魂の最後っ屁みたいなものだろう。イタチの最後っ屁みたいだな、。あああのトビ(またの名をマダラのまたの名をオビトのまたの名を黒ゼツの)のセリフは場面のシリアスさのギャップも相まって思い出し笑いを禁じ得ないな。
きのこ帝国の、日本ロックバンドの、日本戦後文化の、最後っ屁。1stアルバムの「渦になる」から「退屈しのぎ」。
生ぬるい惰性で生活を綻ばすゴミ箱みたいな部屋の中から
時が過ぎるのただただ待ってるそれだけ
眠れない夜更けに呼吸のおとを聞く
許せない言葉もやるせない思いも
いずれは薄れて忘れていくだろう
でもたまに思い出しお前に問いかける
憎しみより深い幸福はあるのかい
-きのこ帝国 “退屈しのぎ”-

9月は三島由紀夫の小説を読み漁った。
『仮面の告白』『金閣寺』『鏡子の家』『潮騒』『豊饒の海 春の雪』『豊饒の海 奔馬』『豊饒の海 暁の寺』『豊饒の海 天人五衰』『憂国』『午後の曳航』『葉隠入門』
日本の失われつつあった古典的美を追求した川端康成や谷崎潤一郎らの流れを汲んでいると思われる。実際に谷崎には非公式とはいえノーベル文学賞への推薦文を書いたようであるし、川端がノーベル賞を受賞したときには川端邸で対談も行っており、文学的方向性が近接していることは疑えない。そもそも三島由紀夫の才能を発掘したのも川端だったこともあることからして、日本の古典的美学をさらに突き進めていった小説家という認識で問題ない。
三島自身、昭和とともに生まれ戦争を経験しながら戦地に赴くことなく敗戦、程なくして『仮面の告白』などの代表作を残していく時代にあって、そして戦後のアメリカ占領とともに日本文化がさらに喪失していく時代にあって、微細な情景描写が過剰なまでに詰め込まれていくというのは故なしとしないのだろうと思った。
川端の代表作『雪国』(冒頭の有名な作品「国境のトンネルを抜けると雪国であった」)の簡単な評論を三島が書いている文章をwikipediaで拝見したが、冒頭近くの「電車の窓に映る大文字焼きの情景」に関する記述は川端の情景描写の巧みさを秀逸に評しているのには舌を巻いた。優れた小説家であるとともに、優れた批評家でもあるようだ。もちろん川端の「日本の美」に関する評論も、谷崎の「陰翳礼讃」も同じく優れた批評家である一面を表しているので、三島に限ったものではないが。
文学の評論や日本の古典的美学に関する評論は、日本文学者であればおのずと導かれるはずであるのは疑いようのないこととして、やはり三島の三島たる所以は、楯の会を組織することとなった保守的思想・日本の憲法や防衛論、独自の天皇論・そしてまた、思想的な認識で終わることのなかった行為としての武士道的自決、となるのはいうまでもないことと思う。三島生誕100年という記念すべき年であるということもさることながら、死後50年という月日が経っていることから、自然と三島の考えとは距離をとりながら、そもそもこの時代に英雄的自決なんてものは、保守的思想なんてものは流行らないということもあるが、彼の考え方と遠く隔たったこの時代から冷めた目で見渡そうとするにつけても、僕としてはどうにもこうにも彼の心や魂そのものが訴えかける本質的な問題にたいてして冷淡な態度ではどうしてもいられないという気がしてならない。
日本の古典的美学を突き詰めていった先に到達した武士道的苛烈な最期というものは、日本の美が情景描写や自然との一体というソフトで柔らかな側面とそしてその裏に隠されたディープでハードな武士道的精神の忘れてはならない二面性を最も激烈な形で表したと思う。日本というものを誰よりも意識した三島にとって、それは単なる情景描写や自然への愛着に終始するわけにはいかなかったのだというのは頷ける。特攻隊にのって英雄的な死を遂げていく若者が日々映っていたであろう彼の心には、日本をソフトな側面だけに押し留めておくことはできなかった。さすれば武士道的な精神とは何であるか。三島は『葉隠入門』の中で武士道の原典ともいうべき『葉隠』を引用しながらその本質を突き止めて我が物にしようと、自分の魂に取り込むように論じている。「武士道とは死ぬることと見つけたり」という有名な一文もあり、または吉田松陰の激烈な革命思想をも引用しながらかく述べている。
「この説に従へば、この世には二種の人間があるのである。心が死んで肉体の生きてゐる人間と、肉体が死んで心の生きてゐる人間と。心も肉体も両方生きてゐることは実にむづかしい。生きてゐる作家はさうあるべきだが、心も肉体も共に生きてゐる作家は沢山はゐない。作家の場合、困つたことに、肉体が死んでも、作品が残る。心が残らないで、作品だけ残るとは、何と不気味なことであらうか。又、心が死んで、肉体が生きてゐるとして、なほ心が生きてゐたころの作品と共存して生きてゆかねばならぬとは、何と醜怪なことであらう。作家の人生は、生きてゐても死んでゐても、吉田松陰のやうに透明な行動家の人生とは比較にならないのである。生きながら魂の死を、その死の経過を、存分に味はふことが作家の宿命であるとすれば、これほど呪はれた人生もあるまい。
— 三島由紀夫「小説とは何か 十一」
「心が死んで肉体の生きている人間と、肉体が死んで生きている人間と」
僕にはこの言葉が脳裏を焼き付けてなかなか離れていってくれない。三島の解釈とはもちろん異なるだろうけれども、自分の生き方僕らの時代の生き方そのものと照らし合わせてみるにつけて、意義ない言葉とは思われない。
三島は激烈な死を以って、肉体は死するとも、魂は今なおこの世にとどめさせんとした。
そして僕の心に、僕の魂に濃く、鋭く刻みつけた。肉体滅ぶとも、魂滅びず。
いやはや、僕の心は何を思う。魂は何を叫ぶ。
魂の死せんとしながら、肉体のみ生きたり。これいかんせん。


































のように、眼前に滞る無機質な時の流れが、ねずみ色の世界を形作る-150x150.jpg)