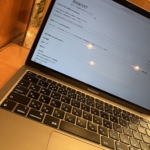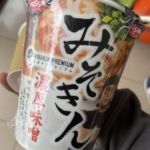僕は一仕事終えて、束の間の休息を取りに職場から飛び出る。キンと冷える空気に包まれると同時に、澄んだ夜空から降り注ぐ月明かりに目を奪われる。足早に帰路を急ぐサラリーマンたちと、これからまた一仕事こなさなければいけない僕と、月明かりはその間の明暗を分ける目印みたいに煌々(こうこう)とアスファルトを照らす。家族連れの子供たちと、突き出た長ネギを買い物袋から落とすまいと歩を進めるをお母さん横目に見て、これから家に帰って家族団欒幸せな夕食が始まるんだろうと想像するに、それと対をなすかのような自分が惨めで、暗いロングコートに身を包む自分が余計に哀れに、そして月明かりのせいか妙に輪郭がくっきりと浮かんでいた。駅前の喫煙所までは少しく時間がかかる。その道中、寒さに震えていてもたってもいられずに身を屈める。ロングコートのポケットに手を突っ込んで、スマートフォンの微かな温かみを感じるとともに、僕を慰めてくれるものがこんなちっぽけなものぐらいしかないのか、と埋められることのない心にポッカリと空いた空白を白い息で寒々した空気の中で虚しく感じ取った。

ふいに風が吹き荒れて一瞬時が止まったように、周りの雑音がノイズキャンセリングされたみたいに無音が訪れる。それに合わせて突然、後ろから足音が近づいてきて、
「仕事中にどこ行くんですか?」
ハッと驚きながらもすぐに君の声だと分かった。颯爽と現れる彗星の如く、君が月明かりと僕の間に入り込んでくる。君は少しく恥ずかしそうにはにかんだ表情をしながら、急ぎ足のせいか髪が後ろに乱れながら僕の目を覗き込んでくる。その瞬間はドラマのワンシーンを見ているかのように、美しかった。

あえて僕のことを追いかけてくれて尚且つ話しかけてくれるというのが素直に嬉しい。君にとって僕はどんな存在なんだろう・・・。それは多分・・・月明かりが教えてくれる。
君の行動に驚きながらも興奮を抑えて、
「ちょっとだけ一服したいんだ」
いつもより声が上擦ってしまったかもしれない。ドラマのワンシーンというわけには行かない。もちろんリハーサルなんてしてしなかった。
「そうなんですね〜、私はこれからマックで作業をして、その後また商談があるんです」
職場で話すときと同じトーンで話しているにも関わらず、外で話す時の彼女の声の響きは、幾分大人っぽく感じられる。「マック」が「スタバ」と同じくらいの上品さを兼ね備えているようだった。
風が僕らの前を通り過ぎて、それに合わせて車が前を横切る。僕らは横断歩道の前で一旦歩を止める。風に誘われるように顔を君の方に合わせてじっくり見つめ直す。月明かりが彼女の顔を照らして、可憐な茶色い瞳が僕を吸い込むように膨らんでいく。猫のまん丸い夜の瞳と見分けがつかなくなったところで、我に返り、また前に歩を進める。前を見ながら僕は君の顔を思い浮かべて、夏の頃より随分伸びきった長い髪が、美しく月明かりを照り返して、さらに僕の心をも明るく照らしてくれているかのようだと感じた。

「あっちに喫煙所があるんだ。少し遠いけどそこまで行かないといけない」
「そこらへんで吸っちゃダメなんですか?」
「うん、ダメだね、他の人はそこら辺で吸ってるみたいだけどさ」
喫煙所までの最短距離を考えると、右手にある信号を渡らずにまっすぐ進まないといけない。ただ即座に別ルートを選ぶことにする。それはもちろん、彼女と一緒にいる時間を少しでも長くしたいと思うから、ほんの数十秒の違いなのだが、その一瞬は僕にとって一生よりも長く濃厚な時間になるはずだと感じられる。
すぐに信号が青になって横断歩道をゆっくり進む。信号は急いでる時に限って延々と変わらず、急いでない時に限ってすぐに変わる。世の常だ。
「楽しいな」
「何が?」
「いや、一緒にいられるということそのものが」
「うん、私も」
道行く人の視線も気に止めてはいるものの、僕ははにかみながらその言葉を心の中でもう一度深く味わった。「うん、私も」
別れ際、君は立ち止まって、
「一緒に行こうよ、マックはすぐそこだよ」
突然の誘いに困惑しつつも
「それは・・・月明かりに相談しないといけない。」


































のように、眼前に滞る無機質な時の流れが、ねずみ色の世界を形作る-150x150.jpg)